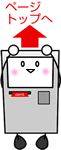自己破産してしまう人に見られる特徴とその原因とは?
更新日:2024/03/18
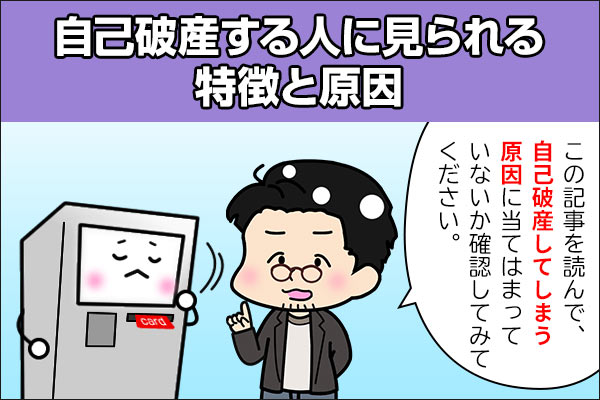
自己破産は貸金業法が改正になってから減少していますが、まったくなくなったわけではありません。
自己破産の原因は借金問題であることは間違いありませんが、債務が返済できなくなる理由は様々です。
また、自己破産をする人には特徴があるのでしょうか?
今回や自己破産の原因や自己破産者の特徴について考察してみましょう。

自己破産とは?
そもそも自己破産というのは債務整理のひとつの手段として認識されていますが、本来破産の申立ては債権者による取り立ての手段でした。
まずは自己破産の基本からおさらいしてみましょう。
取り立て手段としての破産申立て
債務者に資産があることが明らかな場合、その資産を強制的に処分して債務に充当するのが本来の破産申立てです。
つまり債権者が債権を取り立てる方法として破産を申立てていたのです。
生活に必要な資金を一部残して資産を処分した後は、残りの債務が免除される、つまり返済義務がなくなるのが破産です。
債権者が申立てる破産では資産がない者に対しては行いませんが、債務免除が目的で行う自己破産は資産を持たない債務者にとっては効果が高くなります。
極端に言えば何のペナルティもなく債務が免除されるからです。
自己破産の申立て中は職に制限がありますが、免責が確定すればどんな職業にも就くことができ、解雇されることもありません。
自己破産は資産のない債務者にとってはメリットが大きい債務整理方法です。
免責は必ず認められるわけではない
自己破産は申立て手続きをしただけでは債務が免除されません。
最終的に免責が認められなければ返済義務が残るので自己破産をした意味がなくなることになります。
最終的に免責決定が行われれば債務が免除されますが、免責不許可事由に該当すると免責が不許可となります。
免責不許可事由に該当するのは主に次の6つとなります。
- 財産の隠匿
- 換金行為
- 偏頗弁済(へんぱべんさい)
- ギャンブルや浪費による債務
- 詐欺的な借入
- その他手続き上の虚偽
財産を隠すといった行為はもちろんですが、クレジットカードのショッピング枠を現金化するといった換金行為も免責不許可の原因となります。
もちろんギャンブルや浪費といった理由の借金も認められず、かたよった債権者に弁済していても免責が不許可となります。
簡単にまとめると、ずるい行為や自分の楽しみだけで借金を作った場合は免責が認められませんが、それ以外の場合はほとんど免責が認められるということになります。
免責許可後一定期間はローンやクレジットは利用できない
自己破産の申立て開始や免責決定の情報は官報に記載されるので、一般公開されることになります。
しかし、一般的には官報を購読している人はほとんどいません。
自己破産の理由
自己破産がどのようなものかを理解した上で、自己破産を選択する理由について考えてみましょう。
多重債務の原因ランキング
2020年度の日本弁護士連合会(日弁連)のデータによると、多重債務の原因は以下のランキングとなります。
| 順位 | 負債原因 | 人数比 |
|---|---|---|
| 1位 | 生活苦・低所得 | 61.69% |
| 2位 | 病気・医療費 | 23.31% |
| 3位 | 負債の返済(保証以外) | 20.48% |
| 4位 | 失業・転職 | 17.58% |
| 5位 | 事業資金 | 16.13% |
上記以外ではギャンブルが7.18%、浪費・遊興費が11.37%となっていて、借金はギャンブルが原因というイメージは実際には違うことがわかります。
圧倒的に多重債務の原因となっているのは生活苦によるもので、生活費のための借金が多重債務となり自己破産につながっています。
多重債務による自己破産
貸金業法の改正で消費者金融では年収の1/3までの貸付が上限となっていますが、銀行カードローンは規制の対象外となっています。
実際に金融庁の調査では、年収と同額の利用枠のカードローンを発行する銀行も多いという事実があります。
つまり貸金業法改正以降も、多重債務者になる可能性はなくなっていないということになります。
多重債務は過去も自己破産の主な原因でしたが、今でも同様に多重債務が自己破産の原因となっている可能性は高いのです。
特に不動産などの資産を持たない債務者は、自己破産によって免責のメリットだけを得ることができるので自己破産の申請をしやすいと言えます。
それではどんなケースで多重債務に陥るのでしょうか?
まずは返済能力以上の借入をしてしまうことが多重債務の原因となります。
しかしカードローン審査では返済能力を判断してカード発行するので、最初から返済能力がないことは考えられません。
ほとんどの場合はリストラや退職、病気やケガなどで収入が減少して債務金額に返済額が追いつかなくなったことが原因で多重債務になるのです。
生活費のために借り入れをすると、返済財源がないため借金返済のための借入が続くことになります。
これがさらに借金を増やす原因となって悪循環が続き、債務超過となって自己破産に至るケースが多いのです。
自己破産者の傾向
自己破産者というとギャンブルや浪費家、最近では買い物依存症といったイメージがありますが、意外に真面目な性格な人でも自己破産に至るケースが多いのです。
真面目で責任感が強いほど、誰にも相談できずにひとりで借金問題を抱え込んでしまい取り返しがつかない状態に陥ってしまいます。
お金を借りたらきちんと返すという意識が強いためですが、きちんと支払いができなくなった時に早めに専門家に相談すると自己破産に至る前に解決します。
最近では無料で借金相談ができる法テラス、日本クレジットカウンセリング協会や各自治体でも独自に無料相談窓口を設置しています。
また、消費者金融や金融機関ではリスケジュール(リスケ)という契約変更も可能なので、事情を相談することで月々の返済金額を減額することもできます。
自己破産を避けるには早めに債権者や弁護士に相談することが最も効果が高いのです。
自分の債務ではなくても自己破産の可能性がある
自分で借金していなくても自己破産になるケースも存在します。それは連帯保証人となった場合です。
保証人には連帯保証人と単純保証人がありますが、連帯保証人は債務者とほとんど同じ責任があります。
法律的には主債務者に請求せずに最初から連帯保証人に請求することも可能です。
債権者は主債務者と連帯保証人の内、返済能力が高い方に請求することができるのです。
もちろん一般的には最初から連帯保証人に請求する消費者金融も金融機関もありませんが、主債務者が延滞をすれば連帯保証人にも請求が行われることになります。
連帯保証人は「先に主債務者に請求してくれ」といった主張もできず、債権額を全額支払う義務があります。
つまり連帯保証人になるということは、主債務者と同じ金額の借金を背負うことになるということです。
しかも、借りたお金は1円も使うこともできないので、まったくメリットはありません。
主債務者が行方不明等の場合は急に高額な借金の返済に迫られることになるので、連帯保証人が原因で自己破産するというケースも少なからずあるのです。
自己破産のペナルティ
自己破産をしても法律的なペナルティはひとつもありません。
資産を処分されるというのが唯一のペナルティと言えますが、それ以外に市民権を剥奪される、特定の職業に就けないといったペナルティはまったくありません。
公務員であっても自己破産をしたということが原因で職を失うことはないのです。
しかし、個人信用情報機関に記録されることで一定期間クレジットやローンの利用ができなくなるというペナルティはあります。
ただし免責によって債務が免除されるメリットに比べると大きなデメリットではなく、一定期間を経過すればローンやクレジットも利用できる可能性があります。
借金問題を自分だけで解決しようとしてヤミ金融を利用することはトラブルを大きくするだけです。
債務整理の方法は自己破産だけでなく任意整理や個人再生などもあるので、資産状況や負債額に応じて専門家に相談して適切な方法を選択しましょう。
まとめ
最近では日本学生支援機構も個人信用情報機関のKSCに加盟して奨学金の延滞情報を登録しているという事実があります。
それだけ多重債務になる原因が増えているということにもなり、カードローンやクレジットカードのキャッシングだけが多重債務の原因ではなくなってきています。
しかしそれでも自殺者が増加して社会問題になった頃に比べると、自己破産者も減少しているのは事実です。
自己破産しないためにも多重債務になる原因をよく理解して、それを避けるための知識を身につけておきましょう。